
「みらいキャンパス」は、岡山県総合教育センターが運営する不登校生の居場所「まんまリンク」にレッスンを提供しました。「まんまリンク」は、仮想空間 ovice(オヴィス)上で、子どもたちが月数回のイベントに参加したり、スタッフとおしゃべりしたりできる場所です。
昨年は、みらいキャンパス講師 織田尭氏がアート講座を開催。今年は継続企画として、織田講師のアート講座に加えて、あべまり講師によるサイエンス講座を 6 月8 月に 2 回実施しました。今回は、あべまり講師、まんまリンクご担当の竹内愛さん(たけさん)、みらいキャンパス学び開発ディレクター高田七生が、2 回の講座を振り返ります。

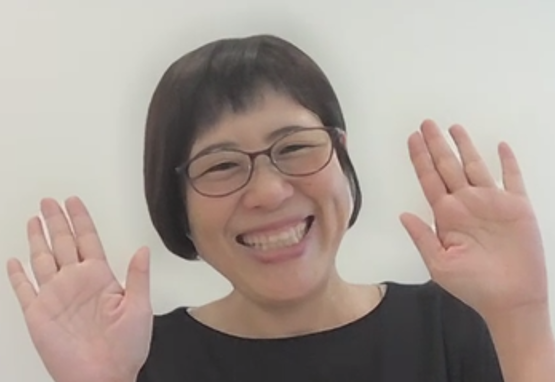
― 1 回目のレッスンはアイス作り、2 回目はペーパークロマトグラフィーの実験でした。たけさんは、子どもたちと同じように参加されていましたが、いかがでしたか?
たけさん(岡山県総合教育センター):
あべまり講師からいくつかレッスン案を出していただき、その中からまんまリンクとして選んだのがこの 2 つでした。1 回目のアイス作りは生活に身近で、みんなが好きなテーマ。終わった後に「家でもやってみたい」と思える内容だと感じ、選びました。2 回目のペーパークロマトグラフィーは、準備が簡単で変化が見やすい点が魅力でした。低学年から中学生まで幅広い子どもたちが一緒に参加するので、誰にとってもわかりやすく、楽しめる内容にしたいと考えました。
実際にやってみると、私自身も初めての体験でとても楽しかったです! インクがじわじわとにじんでいく様子に「わあ!」と声が出るくらい、子どもたちと同じ気持ちで驚きました。変化までの時間が短く、結果がはっきり見えるので、子どもたちの反応もとても良かったと思います。
正直、「今日はどんな子が何人来るかな」と毎回少しドキドキしていましたが、いざ始まると私自身も夢中になってしまって……。大人も一緒になってこんなに楽しめるレッスンを提供していただき、感謝の気持ちでいっぱいです。
あべまり講師:
そう言っていただけて嬉しいです。どんな場面でも大切にしているのは、子どもたちが「自分で見つけた!」という体験ができることです。動画で知識を得るだけでなく、自分の手元で確かめたり、色の変化を目の前で見たりすることで、発見が自分ごとになり、感動や記憶と結びつきます。今回のペーパークロマトグラフィーでも、「何色が出るかな?」と予想しながら観察できるようにしました。
一方で進行案は、普段よりゆったりと作り、状況に合わせて自由に調整できるようにしました。子どもたちは日によって体調や気持ちが違います。自己紹介で盛り上がれば時間をたっぷり取り、逆に実験の一部は見せるだけにして進行を変える。その日の子どもたちに合った“濃度”で授業を進めることを意識しました。
― 2 回のレッスンを終えて、印象に残ったことを教えてください。
あべまり講師:
2回目のレッスンでは、自己紹介をしてくれた人たちがいましたよね。あれは本当にびっくりしました。「こんなふうに自己開示してくれるの? しかも会うのが 2 回目の私に?」と、想像以上のことでした。自己紹介は、リラックスして「ここで自分は認められている」と感じないとなかなかできないこと。しかも手元の文章をただ貼り付けるのではなく、自分の言葉を付け加えながら、ゆっくりでも頑張って入力して共有してくれた。その姿がとても印象的でした。
たけさん(岡山県総合教育センター):
その場面、私も一番印象に残っています。6月に実施した1回目のレッスンでは、子どもたちの中には、実験よりも「他の人と話したい」という思いの子もいて、その思いをあべまり講師やスタッフに率直に伝えていたように感じました。大人に向けて「自分たちの思いを聞いてほしい」という気持ちの表れだったように思います。
でも、そこからまんまリンクの大人との関係性も少しずつ変わり、「ここはありのままの自分を認められる場だ」ということをより感じられるようになってきたのかもしれません。2回目のレッスンで「自己紹介してみようかな」と言ったその発言をあべまり講師がしっかりと受けとめてくださり、場の雰囲気がふわっとやわらかくなりました。
レッスン後、スタッフ同士でも「あの瞬間から場が変わったよね」と話しました。子どもたちも、「自分の気持ちや言葉を大人がちゃんと受けとめてくれるんだ」と実感できたのではないかと思います。
あべまり講師:
ありがとうございます。 まさに、この機を逃してはいけないと思ったんですよね。 もちろん今回のレッスンの目的は、科学というコンテンツを楽しんでもらい、発見する喜びを感じてもらうこと。でも、まんまリンクさんに通う子どもたちの様子を考えると、自分から話してくれた瞬間は、とても大事なきっかけだと思いました。だからこそ、他の活動の時間を少し減らしてでも、この時間を大切にして一緒に深めることで、子どもたちが「ここは安心できる場所だ」と感じてもらいたいと考えてレッスンを進めました。
実際2回目は、講座のあちこちで「やってみたい」という気持ちがあふれていて、「材料がないけど、家に帰ったらやってみる」「手元にあるものでやってみたい」と言ってくれる子もいるなど、前向きな参加意欲を感じる場面がたくさんありました。
高田七生(みらいキャンパス 講座開発リーダー):)
私もあの自己紹介の瞬間には感動しました。日頃からスタッフの皆さまが大切にしてきた「安心感づくり」の積み重ねがあったからこそ生まれた行動だと思います。「ここならありのままの自分で大丈夫」という気持ちが子どもたちの中に根付いているからこそ、会うのが 2 回目の大人でも心を開けるのだと感じました。
さらに、あべまり講師の「あなたのことが知りたい」という気持ちが、言葉や表情、すべてのふるまいからあふれていたことにも感動しました。実験中も自己紹介のときも「それ教えて!」「もっと知りたい!」という空気が子どもたちに伝わり、もっと話したくなる、もっと自己開示したくなる雰囲気が生まれていました。
― まんまリンクでみらいキャンパスのレッスンを実施したことについて、感じたことがあれば教えてください。
たけさん(岡山県総合教育センター):
スタッフ以外の大人と関わること自体が、子どもたちにとって貴重な経験だと思います。また昨年は 1 回だったレッスンが今年は 2 回になり、1 回目と 2 回目の間で子どもたちの雰囲気や取り組み方が少しずつ変化していく様子を感じられたのもよかったです。
1 回目のレッスンはおしゃべりを楽しみたい気持ちが強く、実験に気持ちが向かない様子も見えました。レッスン後「ちょっとおしゃべりしすぎたかな…」と思っていた子もいると思いますが、それを厳しく注意するのではなく、受けとめることを意識しました。
いろいろな大人との接点の中で認められる経験が、子どもたちの自信につながり、前向きにやってみようという気持ちと行動になると感じています。
あべまり講師:
1回目と2回目では子どもたちの科学実験への集中度がはっきりと変わりました。 その背景には、「お話できる時間はこのあとあるからね」というたけさんの一言と、何より、まんまリンクのスタッフの皆さんの日々の受けとめとコミュニケーションの積み重ねがあったからだと感じました。
まんまリンクさんが大切な居場所の1つになっているのだと改めて思いましたし、前進している子どもたちの姿に、私も元気をもらいました。
高田七生 :
お二人の話を聞いて、改めて「子どもたちが主体となれる場をつくる」ことの意義を実感しましたし、「主役は子ども」という視点の大切さを再確認しました。
子どもたちが安心して自分を出せるまでには、スタッフの皆さんはじめ、その子をありのままで受けとめる大人とのコミュニケーションの積み重ねが欠かせません。
実験の時間が多少短くなっても、子どもが自分から語ろうとする瞬間を大切にする。大人の予定よりも子どもの声を優先する。子どもを中心とするその姿勢は必ず伝わりますし、一方、こちらが形通りにしようとすると子どもたちは敏感に感じ取ります。「あなたたちのことを本当に知りたい」という気持ちで向き合い続けることが大切だと思いました。
こうして 3 人で振り返る時間を持てたことで、私も温かい気持ちになりましたし、「明日からまたよりよいレッスンをつくっていこう」と思えました。まんまリンクの皆さんと、みらいキャンパスが同じ思いで一緒に場を作れたことが本当に嬉しいです。
インタビュアー&記事執筆 長原典子